ツキノワグマシンポジウム開催されました
 ツキノワグマシンポジウム(以下,シンポ)が2008年6月14日、若桜町で開催されました。
ツキノワグマシンポジウム(以下,シンポ)が2008年6月14日、若桜町で開催されました。
このシンポは鳥取県と若桜町の主催でした。
鳥取県(以下、県)では
2007年10月に「ツキノワグマ保護管理計画 ~人とツキノワグマとの棲み分けによる共存を目指して~ 」(以下、管理計画)を策定し、2008年3月11日に2007年度の「鳥取県ツキノワグマ保護管理検討会」(以下、検討会)を開催し、この会議で管理計画を了承し、2012年3月までの保護管理計画がスタートすることとなりました。
県は管理計画を策定し、広くツキノワグマ(以下、熊)のことを知ってもらおうと県民に呼びかけシンポ開催となったのです。開催場所は鳥取県にあっては毎年数多くの目撃がみられる若桜町とし、基調講演には京都府、兵庫県などで熊の保護管理に携わり、2005年3月に環境省から『ツキノワグマの大量出没に関する調査報告書』(http://www.env.go.jp/nature/report/h17-01/index.html)が報告された際の調査結果の取りまとめにあたった京都大学農学部の高柳敦さん、パネリストは様々な方面から招請、地元で梨を生産している八頭町梨生産部長の松田純一さん、狩猟者の立場から八頭郡猟友会会長の有田敬さん、県の保護管理計画の基礎データを収集し、報告した株式会社野生動物保護管理事務所の片山敦司さん、行政から県生活環境部の長谷川誠さん、基調講演者である京都大学の高柳敦さん、そして民間の(自然保護というカテゴリーに入っていましたが)団体代表として山陰ツキノワグマ研究会(前記括弧内は行政から見た認識ですが)から安田晃、司会およびコーディネーターは鳥取県ツキノワグマ保護管理検討会の会長であった鳥取大学の上原正人さんでした。
 先ずはじめに県生活環境部の長谷川誠さんから「ツキノワグマ保護管理計画 ~人とツキノワグマとの棲み分けによる共存を目指して~ 」を策定した意図を述べました。ツキノワグマによる人身被害の回避や農林業被害の軽減を図るとともに、絶滅のおそれのある地域個体群の長期にわたる安定的維持を図ることによって、人とツキノワグマの棲み分けによる地域の共存を目指す」としています。 保護管理の実施の項では、個体管理を以下のように示しています。①狩猟を禁止する方向で取組を行う。②クマの有害鳥獣捕獲許可権限の見直し(広域的な視点から適切な保護管理を行うため、権限行使のあり方を検討する)。③錯誤捕獲防止対策を推進する。④出没等対策基準に基づき段階的な対応を図る、としています。
先ずはじめに県生活環境部の長谷川誠さんから「ツキノワグマ保護管理計画 ~人とツキノワグマとの棲み分けによる共存を目指して~ 」を策定した意図を述べました。ツキノワグマによる人身被害の回避や農林業被害の軽減を図るとともに、絶滅のおそれのある地域個体群の長期にわたる安定的維持を図ることによって、人とツキノワグマの棲み分けによる地域の共存を目指す」としています。 保護管理の実施の項では、個体管理を以下のように示しています。①狩猟を禁止する方向で取組を行う。②クマの有害鳥獣捕獲許可権限の見直し(広域的な視点から適切な保護管理を行うため、権限行使のあり方を検討する)。③錯誤捕獲防止対策を推進する。④出没等対策基準に基づき段階的な対応を図る、としています。
 基調講演では「野生動物との共存に向けて」と題し述べています。高柳さんは、「私は京都市での特定鳥獣保護管理計画に携わった経験があります。その中で計画を実施する中でいろいろな問題点が出てきました。今回はその問題点の解法をどのように行ってきたかをご説明したく思います。といいますのもこのシンポジウムに参加された皆様地域住民の方々が、県が策定した保護管理計画と向き合わねばならないからです。
基調講演では「野生動物との共存に向けて」と題し述べています。高柳さんは、「私は京都市での特定鳥獣保護管理計画に携わった経験があります。その中で計画を実施する中でいろいろな問題点が出てきました。今回はその問題点の解法をどのように行ってきたかをご説明したく思います。といいますのもこのシンポジウムに参加された皆様地域住民の方々が、県が策定した保護管理計画と向き合わねばならないからです。
私が野生動物との共存を研究した始めた25年前は、地域住民の方々はもちろん、行政機関の人たちも何を言うかという態度でありました。しかし、今は野生動物との共存という言葉に異を唱える人はいないでしょう。しかし、この共存には、野生動物からの耕作地、生産物の防御のように人間の生活を営んでゆく場合の、ある面対決の場も含む大きな枠組みとしてとらえるほうがいいでしょう。
前の世紀、即ち20世紀は自然を利用していた世紀であったように思います。しかし、今の世紀である21世紀は資源プラス我々が必要とする自然を維持する世紀であるように思います。だからこそ、今が表題にもありますように共存の時代ではないかと思います。その点では生物多様性、即ち、様々な生物が生きてゆくことができる環境こそ必要でしょう。
地域にとって熊との共存を考える場合、よく練られた保護管理計画が重要ではありますが、対策の基本としては迅速であること、同時に持続的であること、情報が継続されなければなりません。自身と熱意、これらを行政担当者の方々に求めたく思います。そして地域住民、猟友会、自然関連の団体、行政など様々な人たちが集まって合意形成を行う必要があると感じています。といいますのも、鳥取県においては保護管理計画に基づいて住民、行政など大きな枠組みで動くことは、まだ緒についたばかりであります。その点で、ここにいらっしゃる皆さんの意見、行動が重要となってくると考えます」と話しました。
 若干の休憩を挟み次いでで行われたパネルディスカッションでは、司会の上原さんが、「県内ではイノシシは増え被害も多いが、熊は増えているとの報告はありません。しかし、生ずる被害が大きいのが特徴であり、ここでも人との共存が問題となるでしょう。そのためのディスカッションとしてお聞きください」とはじめました。
若干の休憩を挟み次いでで行われたパネルディスカッションでは、司会の上原さんが、「県内ではイノシシは増え被害も多いが、熊は増えているとの報告はありません。しかし、生ずる被害が大きいのが特徴であり、ここでも人との共存が問題となるでしょう。そのためのディスカッションとしてお聞きください」とはじめました。
県の保護管理計画に関する調査の概要を片山さんが話した後、地域住民の立場から松田さんが、「一昨年度は熊被害が多かった。水田転換によって山間地ではなく平らな水田跡に梨を栽培するようになりました。熊対策(熊だけではなりませんが)に電気柵を設置しますが、未設置の畑から浸入することも見られます。一度梨畑に侵入したら200個近く食べる熊もいます。更に、次の年に実ができるはずの枝をへし折るものもいます。夕方と朝、よく見かけます」と農家の被害の実情を述べています。
次いで、猟友会から有田さんが、「熊に関しては有害駆除処分の依頼がない限り、撃つことはありません。ただ、放獣するという点では、作物被害だけではなく民家周辺の出没など人的被害が十分予想できる件、それが恒常的であれば、あえて放獣することではなく処分もやむをえないでしょう。この処分には被害を繰り返さないという大きな目的があることを県民に理解されなければ、猟友会および猟友会会員にとっても不幸なことです」としています。
そして、片山さんが兵庫県の現状についてコメントしました。彼は、「兵庫県では出没地域での現場対応、あるいは県の計画に対する合意形成などを主目的とした専門員、実務者を設けています。また、兵庫県内での生息頭数調査も行っていますが、精度は高くありません。生息頭数も明確ではないのですが、被害状況と出没頻度など多方面のデータから精度を向上されることができたらと考えています」と述べました。
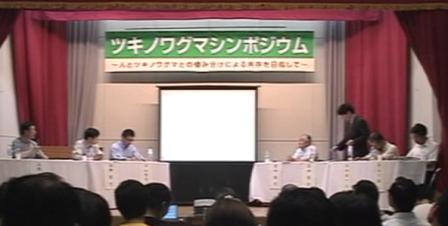 山陰ツキノワグマ研究会(以下、熊研)安田は島根県西部での熊に対する住民の意識調査の結果を示しました。安田は1441名の有効回答から得られた結果として、
山陰ツキノワグマ研究会(以下、熊研)安田は島根県西部での熊に対する住民の意識調査の結果を示しました。安田は1441名の有効回答から得られた結果として、
①
熊嫌う人たち多い。しかし、熊への誤認、被害経験などから嫌いではない選択も。嫌いだが対策を明確にすればと期待している人も。
②
個人で対策費は出したくない? 出さない、少額が7割超、熊のいることの否定・肯定に関わらず
③
行政への期待は大。何とかしてくれ!
④
最多発地域での意見では不要論が多い?
⑤
出没に対する条件整備を望んでいることも
⑥
情報が不足していることからの誤認も
⑦
お金,対策の問題では行政に期待。個人ではどうしようもない?
としました。これらの根拠となる集計結果は機関紙に掲載しています。機関紙希望者はトップページ「会則」にあります会費が必要です、といいますより会員になってください。
 ツキノワグマシンポジウム(以下,シンポ)が2008年6月14日、若桜町で開催されました。
ツキノワグマシンポジウム(以下,シンポ)が2008年6月14日、若桜町で開催されました。 先ずはじめに県生活環境部の長谷川誠さんから「ツキノワグマ保護管理計画 ~人とツキノワグマとの棲み分けによる共存を目指して~ 」を策定した意図を述べました。ツキノワグマによる人身被害の回避や農林業被害の軽減を図るとともに、絶滅のおそれのある地域個体群の長期にわたる安定的維持を図ることによって、人とツキノワグマの棲み分けによる地域の共存を目指す」としています。 保護管理の実施の項では、個体管理を以下のように示しています。①狩猟を禁止する方向で取組を行う。②クマの有害鳥獣捕獲許可権限の見直し(広域的な視点から適切な保護管理を行うため、権限行使のあり方を検討する)。③錯誤捕獲防止対策を推進する。④出没等対策基準に基づき段階的な対応を図る、としています。
先ずはじめに県生活環境部の長谷川誠さんから「ツキノワグマ保護管理計画 ~人とツキノワグマとの棲み分けによる共存を目指して~ 」を策定した意図を述べました。ツキノワグマによる人身被害の回避や農林業被害の軽減を図るとともに、絶滅のおそれのある地域個体群の長期にわたる安定的維持を図ることによって、人とツキノワグマの棲み分けによる地域の共存を目指す」としています。 保護管理の実施の項では、個体管理を以下のように示しています。①狩猟を禁止する方向で取組を行う。②クマの有害鳥獣捕獲許可権限の見直し(広域的な視点から適切な保護管理を行うため、権限行使のあり方を検討する)。③錯誤捕獲防止対策を推進する。④出没等対策基準に基づき段階的な対応を図る、としています。  基調講演では「野生動物との共存に向けて」と題し述べています。高柳さんは、「
基調講演では「野生動物との共存に向けて」と題し述べています。高柳さんは、「 若干の休憩を挟み
若干の休憩を挟み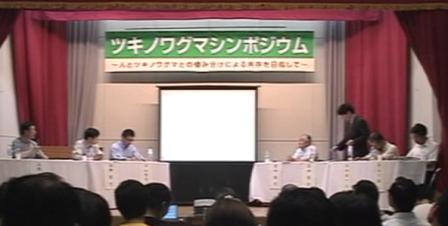 山陰ツキノワグマ研究会(以下、熊研)安田は島根県西部での熊に対する住民の意識調査の結果を示しました。安田は1441名の有効回答から得られた結果として、
山陰ツキノワグマ研究会(以下、熊研)安田は島根県西部での熊に対する住民の意識調査の結果を示しました。安田は1441名の有効回答から得られた結果として、