|

体長1〜2cm淡水性のえびで、色は緑青朱がかった半透明で、5〜6月ごろ水を張った水田に発生し、夏には産卵を終え姿を消す。
豊年えびの卵は、土中で何十年も眠り続け、適した環境になると発生するようです。農薬や化学肥料が少なかった昔は、たまに水田に姿を現した、人々は、豊作の前兆と喜んだそうです。
「豊年えびの起源」
地中」で何十年も眠り続け、適した環境になると発生すること、戦前や江戸時代には、時折水田に発生し稀であったため農民は、豊作の前兆として喜んだこと、砂漠などにその仲間がおり、日本へは弥生時代ごろ、稲作の伝来と共に農具などに付いた土と共に渡ってきたと考えられている。(以上、「豊年えびに出会う旅」より抜粋)
土地に優しくしてあげると、こんなにかわいい出会いがある。
|


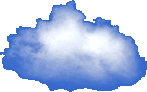


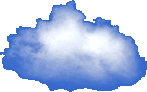
![]()