|
「浄土三部経」についての講話(1)
仏教の本質とは、真実と、真実ならざるものが同時に明らかになること。
真実とは、象徴的には仏。私としては、究極の「無我・慈悲・利他・布施」のこと。そこに真実があり、
それが仏として象徴的にあらわされているのだと思う。
さて、浄土三部経。無量寿経(大無量寿経)、観無量寿経、阿弥陀経、この三つの経を浄土三部経といい、
浄土真宗の根本聖典とされる。
仏教はインドで起こった。経もインドが基である。経の作者は誰か。ひとりか。グループか。
河本さんはグループではないかと言われる。作者は不明である。もと(経の本質)は釈迦が説いていたこと。
仏教学者の藤田宏達さんも、また信楽峻麿さんも言われているが、特に藤田さんの説では、
釈迦がおられた頃、あるいは亡くなられて間なしの頃、阿弥陀や極楽往生の思想も観念も無かっただろうと。
釈迦が説かなかったものを経として作ったのではないかということだ。
釈迦が亡くなって500年、西暦100年頃、釈迦が説いたことにして物語が作られた。
多分、そういうことだろうと思う。それが仏教学の定説だろうと推測する。
観無量寿経でいえば、インドにその原本はない。中国で作られたのではないかという説もある。
大無量寿経でも、差別の記述部分はインドの原本にはなく、中国で作られたのではないかと思われている。
ただ、阿弥陀経は中国で作られたとは聞いていない。
創作の意図は何か。
釈迦が説かなかったという阿弥陀の物語をなぜ大無量寿経は説いたのか。「報正寺通信12月号」
にも書いている通りだが、仏教とは悟りを求めるもの、究極の真実、境地を求めるもの。
人生の「生・老・病・死」の悩みから、いかに脱出するか、解脱するか。釈迦は自ら体得したものを説き、
多くの人々もそれを求めて出家し、あるいは出家までしなくてもそれを体得しようと求めた。人生に疑問をもち、
人間いかに生きるべきかと考えた。
しかし、そのように自覚的に求める人は多くはない。ほとんどの人は食べることに一生懸命精一杯である。
当時のインドは身分制度も厳しく、人間外とされたアウトカーストもいた。人々は、罪を重ね、殺し殺され、奪い奪われ、
差別し差別され、人生の苦悩の中で、喘ぎつつ生きていた。それでせいいっぱいだった。
釈迦のように、人生を断ち切って(出家して)道を求める人は少ない。罪を犯したらバチがあたるのではないかとか、
死後はどうなるのかとか、死んだら先に死んだ人に会えるのかなど、現実の人生の苦しみや死後への不安などに
包まれている人たち。
その人々を導く、救う・・・それは、精神的にも癒され、不安や孤独から解放され、
仏教の目指す解脱の道、煩悩や執着から解き放たれる世界、無我・慈悲・利他・布施に目覚めていくこと。
その道にそって実践していく、そういう自覚をもった人生設計をしていく、人間関係を作っていく、
社会のありようを求める。釈迦の思想はまさにそこにある。どう煩悩から解き放たれ、
人間の尊厳・平等を求めるかということだろう。
経が作られる背景として、そのことが要請されていたのだろう。
出家者のみが救われるのではなく、救いを願うすべての衆生が救われるという阿弥陀仏信仰として
阿弥陀仏物語が作られ、釈迦が語ったものとして伝わってきたのだろう。それに併せて、太陽信仰、
生天思想などが混ざり合って、阿弥陀仏信仰が生まれたと考えられている。
信楽先生がいつも言われることだが、釈迦の死後、出家者ではなく仏教に学ぶ一般の人たちが
釈迦のお骨を分骨し、仏塔を建てた。そして釈迦を偲んだ。その教えは尊いと、永遠化、
超人化されていった。そこで釈迦の教えの尊さを、無限という意味のアミダ、無量寿として表現した。
現実には釈迦は80歳で亡くなったが、その教えは永遠である。教え、願いは世界中に広がっていった。
無我・慈悲・利他・布施の教えとして。普遍的なもの、どこにも通ずる価値、無量光(無限の空間世界)、
無量寿(無限の時間)・・・時空を超えた永遠の真実として人格的に象徴化され、阿弥陀仏と表現された。
釈迦が亡くなられたとき、その分骨された墓の周りに池を作り、飾った。そこが、やがて悟りの場の
象徴表現となった。清浄無垢な世界、極楽として。
経の創作の意図は、そこらにあるだろう。
悟りの世界とは、自他を超えた思想・価値観・道・哲学・倫理などを永遠化、象徴化したものと考えられる。
それへの信仰は多くの人々への癒しであり、導きでもある。生天思想や太陽信仰ともあわさって、
経典に結びついた。一般民衆は経を聴き、読み、信仰ができあがっていった。
「私はこんな不可思議なことをこれまで知らなんだ。孤独、不安や罪への恐怖。この罪深い私を、
目には見えないが、はぐくみ、守ってくださっている。生まれる前から、絶えることなく。
父母が亡くなった今も阿弥陀仏が私を照らしてくださっている。片時も離れず。命が終わった時には、
阿弥陀仏が極楽浄土へ迎えてくださる。仏だけでなく、先だって救われた方々が、浄土の悟りの世界から、
今この私のところまで来て導いていてくださる。なんと有難い、不思議なことであろうか。阿弥陀仏に
空気のように包まれている。大いなるもの、絶対的なものとしての阿弥陀仏がいてくださる。
私に死が訪れても、浄土に迎えられ、仏になるのだ。有難いことである。極楽へ行ってそれで終わりではない。
先立った人に会いまみえ、またこの世に残っている身近な人や多くの人に、絶望の中にいる人たちに、
導きをすることができるのだ。極楽へ行くのは、この世にかえってみんなを導くためなのだ。有難く、
不可思議なことである。自分を大きく包んでくださる阿弥陀仏を感じる信仰。その阿弥陀仏の大慈悲のもとは、
私のかかえている煩悩なのだ。それを御仏が見抜かれて、あなたを必ず救うと言ってくださる。
その阿弥陀仏の大悲へのかたじけなさに、慙愧が生じ、やがてその慙愧と共に自分自身の中にあるエゴ、
醜いもの、それからわずかばかりでも解き放たれていく。そして、よし、その道を歩もう。自分を損ない、
人を損ないしてきた人生を改めて、そういう方向へまっしぐらに行けるか。いや、行けなくて失敗したとしても、
どんなことがあってもはぐくんでくださる御仏に包まれているのだ。この無底、無限、包容、大悲の御仏の
阿弥陀仏に帰依しようではないか」。
このように、民衆は阿弥陀仏信仰に安住していったのであろうと推察する。
人間の、苦悩、悲しみ、絶望、不安があるとき、そこから信仰によって癒されることによって、まことの道へ、
自己の解放へ、社会の解放へ導かれていく。そういう願いと意図をもって、
無量寿経は作られたものと推測する。
無量寿経の大意はどうか。
解説にも記述されているように、「阿弥陀仏のいわれを信ずる。念仏を称える。往生をとげる」ということが
基本だと思う。
観無量寿経も同じ。人間を9通りに分けて説かれているが、そのうち最も下位である「下品下生」であっても
、仏の教えを聞き念仏を称えれば救われるとされる。極悪最下のものも救われる。
阿弥陀経では、十方の諸仏が証明している。阿弥陀のいわれを信仰し、浄土往生をとげること。
三部経は、阿弥陀仏信仰と、念仏して浄土へということだ。
無量寿経のポイントは何か。
阿弥陀仏物語の部分で、釈迦が阿難にこう語った。「はるかな昔、錠光という名の仏が出て、
人々を教え導き、そのすべてにさとりを得させた」と。この世がエゴにまみれ、収奪に明け暮れる闇
であったとき、それを開くために「錠光」(燃灯仏)という名の仏が数限りない人々を教え導いた。
苦悩から解放される道、成仏道、仏になる道、自我のしがらみに束縛されている自分から解放されて
無我に至る道、これが仏への道である。欲望、快楽、財産、名誉、地位、それらの欲求を満足させるのでなく、
自己を解放する、水平社綱領にいう「人間性の原理に覚醒し、人類最高の完成に向かって突進す」ということ、
人間も獣ではあるが人間性の真実を求めていこうとすること。人を導くために、錠光がまずすべての人に
悟りを、解放、解脱の道を得させた。次に光遠という名の仏。永遠の光という名に象徴されている仏である。
そして、月光、栴檀香、善山王・・・とそれぞれ意味をもった53の仏が続く。
54番目に世自在王が出られる。阿弥陀仏の師である。世自在王は、シバ神の別名ともいわれる。
ヒンズー教とのつながりがあるようだ。世自在王は、如来、応供など、十号の呼び方があった。
ひとりの国王が世自在王の説法をきいて深く喜び、国も王の地位も捨て、出家して法蔵と名乗った。
法蔵は後の阿弥陀仏である。無量寿経は、法蔵菩薩の四十八の誓願へと展開するが、
今日の話はここまでとしたい。
「浄土三部経」についての講話(2)
仏教の思想は解放の思想につながる。阿弥陀仏は最も解放された人格を象徴し、浄土は
最も解放された世界を象徴していると受け止められる。その解放された人格、世界を、阿弥陀仏物語として
無量寿経に表現した。その思想や考え方から学び取ることが大事である。
前回は、世自在王が現れる前の数々の仏のところまで話を進めた。今回はその続きとして、
世自在王のところから話を始める。
「そのときひとりの国王がいた」・・・「国王」とは、権力の象徴である。財力の象徴、暴力の象徴でもある。
その時代のトップである存在。その国王が世自在王の説法を聞いて深く喜び、さとりを求める心を起こした。
「世自在王」とは、世において自在である、いろんなものに全く拘束されない、権力にも財力にも暴力にも
左右されない主体性をもつ存在である。そういう仏の説法をきいた。
仏の説法とは何か。その本質、キーワードは究極の「無我・慈悲・利他・布施」であろう。無我とは、
自己中心でないということ。自分のことより他の人のことを考えること。それによって、
次の「慈悲」につながる。慈悲とは、慈しみ、悲しみのこと。それは「利他」を生む。
利他とは他者を助けることであり、「布施」の心につながっている。それらは個々にあるのでなく、
相つながったものとしてある。それは人間性といわれるもの、人間性の原理、本質につながるものである。
仏の説法は、それを語った。象徴的な物語として。
それに対して、「国王」とは。まさしく無我の反対、対極にあるもの。エゴそのもの。権力、地位、財産を
守り拡大するため、他国を侵略し、人を殺し、奪い、頂点に立とうとする。真反対にある。
人間性の原理ではなく、動物性・獣性の原理、弱肉強食の原理に立つ。「報正寺通信1月号」にも書いたが、
「この世はしょせん闘争よ。負けて何になる。勝ってなんぼよ」の世界。慈悲の反対、冷酷無残。
利他どころか利己そのもの。日本のかつての侵略戦争の時代の思想、吉田松陰も木戸孝允も西郷隆盛
もそうだったろう。江華島事件を機に日本が朝鮮に進出し、火を放ち、武器を略奪した、
そういうものが国王の世界だ。真実の世界とそうでない世界とを対比し、象徴的に表現している。
仏の説法を聞いて、国王は反発したのではなく、うなずき喜んだ。普通なら世界が違うと怒り、
世自在王を殺しただろう。しかしそうではなかった。国王の物の見方が変わった。
曹洞宗町田宗夫さんが世界宗教者平和会議で「部落差別はない」と差別発言をして糾弾を受け、
大きく反省をし、人間変革をしたと聞いているが、そのように見方が変わった。それを「喜び」と表現している。
それは、私たちの中で、どうであろうか。戦争を肯定していたものが、反対の話を聞いて平和にめざめ、
喜ぶ。そういう人が周りにどれほどいるだろうか。
人間変革ということ。自覚を求める心を起こした、さとりを求める心が生まれた、そして王位を去った。
自らを解放したのだ。自分を縛っていた国から自らを解き放って、全世界の立場に立った。出家ということだ。
求めるものが変わった。自己実現を求める人になり、法蔵と名乗って修行者となった。権力にはもどらない。
その決意は固く、一筋に真実なるものを、自己においても世界においても完成させようと求めた。
次に法蔵菩薩は世自在王の徳をほめたたえた。讃仏偈といわれるものであるが、ここではふれる
時間がないので次へ進み、法蔵菩薩の四十八願について話をする。
四十八願とは、法蔵が修行して阿弥陀仏になるというとき、自分はどういう人格、社会を形成するか
ということを、48通りに表現したものだ。そのいくつかについてふれよう。
(1)は、「地獄・餓鬼・畜生のものがいるようなら、私は仏にならない」という。経典作者がこう著した
ということは、インド社会に地獄・餓鬼・畜生と表現するほかはない過酷な現実があったということだ。
これが解放されなければと思ったのだ。地獄とは、人間として最低最悪の世界、
そこには痛め痛めつけられる鬼と罪人、責めるもの責められるもののみ、鬼と亡者しかない。
真実を求めて向上していこうとすることすらない。地獄、言い換えて戦争と言ってもよい。餓鬼、
それは餓えであり飢餓である。畜生、それは怖れであり差別である。自分が最も可愛く、他といつも争い、
他を尊重することはない。・・・戦争と、飢餓と、差別。(1)においてこれを取り上げた意味を、
考えさせてもらうことができる。「地獄」といえば特別な世界を昔の人は考えただろうが、今は社会の中に
それを見届けること、社会の中でそれを把握することが必要だ。最も最初にこのことが挙げられていること、
現実の人間の苦悩、社会の苦悩の問題が、救いの対象として挙げられていることに
注目しなければならない。それは(2)でも繰り返されている。
(3)では「人々がすべて金色に輝く身となる」ことを挙げている。「皆をすべて輝かせる」というのだ。
ある人は暗い隅に追いやられるとかのことはない。それぞれが違っていても、皆を輝かせたいと言っている。
(4)では「人々の姿かたちがまちまちで、美醜があるようなら」さとりをひらかないと言っている。
これは皆が同じで差がないことを求めているようであるが、今の時代から言うならば、違いがあっても違いが
尊重され、美しいとか才能があるとかスタイルがいいとかでもてはやされたり排除されたりすることはない、
それによって劣等感をもったりいがみあったりすることがない社会にするということだろう。
「皆同じ顔・かたち」になる・・・ともとれるが、それはどうだろうか。「たとえ、色や形が違っていても
みな大事にされ、障害があっても尊ばれる。違うままに尊重される」ということでなければならないだろう。
経典作者の限界といえるかもしれない。
時間的にすべてにふれることができないので(35)の女性差別のところへとぶ。
(35)では、「女性が、・・・命を終えて後に再び女性の身になるようなら」さとりをひらかないと言う。
これこそ、経典作者の限界であろう。「再び女性にはしない」と女性を否定する。女性は汚れたものという
当時の社会の差別観念がそのようにさせたのだろう。本当ならば、女性は汚れたものという偏見から
解き放たれ、堂々と偏見を打ち破り、男女ともに解放される視点でなければならなかった。
そういう世界にならなければ仏にならないというべきであろう。このような誤った内容に基づいて、
「浄土へ参ったら女性はいない」という論が出てきた。次にふれる(41)と同じく差別そのものの考え方である。
(41)は、「その身に不自由なところがあるようなら」さとりをひらかないと言う。
だから「浄土には障害者はいない」という論者が出る。善意でとらえるならばいろんなハンディがないように
ということかもしれないが、本来ならば、どのような障害があろうと志を起こして精進すれば仏になれると
言うべきだ。この(35)(41)を額面通りに受け取った僧は「極楽には女性も障害者もいない」と説き、
マイナスイメージをふりまいた。
(43)には、「人々に尊ばれる家に生まれることができる」とある。これも問題である。
「尊ばれる家」の反対は「蔑まれる家」であろう。当時のインド社会の身分制度でいえば、
奴隷制度やアウトカーストとされる
旃陀羅の家もあった。それをそのまま認めたうえで「尊い家にうまれるように」と読める。ここでもインド社会の
差別意識をそのまま受容している。善意に解釈すれば、たとえ旃陀羅の家でも王の家でも譲り合い分かち合う
心を大事にし家族みんなが尊重し合う家が尊ばれる家であり、王の家でも争いが絶えない家は尊ばれる家
ではないということか。このとらえにも無理があるだろう。差別観念に基づくものとして問題を残している。
質問に答えて、(18)の願についてふれたい。浄土真宗にとって、この第十八の願は根本の願であり、
王本願と呼ばれるものである。
「わたしが仏になるとき、すべての人々が心から信じて、わたしの国に生まれたいと願い、わずか十回でも
念仏して、もし生まれることができないようなら、わたしは決してさとりを開きません。ただし、五逆の罪を
犯したり、仏の教えを謗るものだけは除かれます」。
「すべての人々」・・・十方衆生、そこに意味がある。たとえ宗教が違っても、民族が違っても、その
人たちが、私の世界である浄土がすばらしいと、なんと尊い仏かと、心から信じ、納得して、ここに最高の
人格・世界があると、ここにこそ帰依する、求める世界があると思い、ここに生まれたいと、いじめも差別も
ないこの世界に生まれたいと腹の底から願い、1回でも10回でも、阿弥陀仏よと心に思い、
南無阿弥陀仏と念ずる。目覚め、自覚が生じた人、人格主体が確立した人、そういう人が私の国に生まれ
損ねるようだったら、私は仏にならない。私の世界を仰ぎ尊ぶすべての人を浄土へ生まれさせる。
私が仏になるということはそういうことだ。すべての人を、最高の自己完成に、世界に導いていく。
ただ、皆をそのようにしたいが、現実にはそうはいかない。自覚する道を失い、父母や覚った僧を殺す、
仏身を出血させる、和合を破る、五逆罪や教団や仏教を謗るなどの罪を犯した人は救わないという。
経典作者はその生き方を、まことの道ではないと戒めているには違いないが、仏の深い慈悲からすれば、
仏教にまなこを開くことのない人、煩悩にとらわれ、人を羨み、敵意を持つ者。私も、本願寺に対して、悲嘆、
慈悲の発想ではなく、つい悪口を言ったりすることがある。それは五逆罪の一つ、和合を破る、仏教教団の
秩序破壊の方向と言える。家族の中でも、親を謗ったりする。五逆である。そういう煩悩に翻弄されている。
しかし、そういうあなたを見捨てることはない、そういうあなたにこそ、仏の涙は注がれているのだ。
唯除という排斥の表現の中に、仏は大きく涙を流しながら、決して捨て去ることはない。仏の国に迎え、
仏にさせる。そういう深い慈悲がある限り、唯除五逆とは人間へのブレーキであると言える。
母が、「あんたは、もう知らん」と子を叱る。しかし、本来は無限の愛情で子を包んでいる。
阿弥陀仏も、慈しみ、悲しみの中で私たちすべてを包んでいるという慈悲の表現なのだ。
「浄土三部経」についての講話(3)
今回は、「浄土三部経」の、問題と思われるところについて何点か述べたい。
まず、法蔵菩薩の修行について。〔九〕の後半に、「法蔵菩薩は、はかり知れない長い年月の間功徳を
積み重ね、その間、あるときは富豪となり、在家信者となり、バラモンとなり大臣となり、国王や転輪聖王
となり、六欲天や梵天の王となり・・・」とある。法蔵菩薩は、金持ちになったり一般庶民になったりしながら、
仏の道を求めたというのだ。また古代インドの四姓制度の最上位身分であるバラモンとして、
祭祀を行うつとめをしたりしたという。バラモンは白人系のアーリア人種であり、インド先住民を支配して、
バラモンを頂点とする身分制度社会を形成した。そういうバラモンにもなり、大臣にもなった。富豪、バラモン、
大臣・・・みな上流でありエリートである。さらには国王、これは最高権力者であり支配階級である。
転輪聖王は「正法によって全世界を統治するといわれる王者」と註釈にあるように、仏教以前からインドの
王者である。「六欲天や梵天の王」もそうであり、それらはインドにおいては宇宙を支配する神である。
これらから、法蔵菩薩が阿弥陀仏になるまでの修行は、常に「上層のもの」に生まれ変わって
なされていることがよみとれる。それが修行にとって意味があり効果があると、経典作者たちが
考えたからだろう。
しかし本当の意味の修行とは何か。支配者や権力者の側ばかりに生まれ変わっていたら、本当の修行は
できまい。虐げられた側、障害がある者、ハンディがある人、その苦悩の場へ身をおいてこそ、
本当の修行になるのではないか。苦悩の中で自らを陶冶し、最高の人間・人格を求めるべきではないか。
それなら分かる。しかしそうでないところに、経典を作った人たちの思想に問題があると思わざるを得ない。
次に、〔二七〕の後段、「まるで生まれながらに目の見えない人が、人を導こうとするようなもの」
という部分について。「仏以下のものが仏の心を推察することはとてもできはしない」ということを言おうとして、
「目の見えない人」をたとえにし、貶めているのだ。「目が見えない」というハンディに対して何の配慮もない。
もっと別なたとえをすべきであろう。「幼児が大人を導けないように」とか。目が見えないことの悲しみやつらさ
を考えようともしていない表現である。
同様の問題が、この前の同朋三者懇話会でも話し合われた。部落解放同盟広島県連から資料が出され、
「重誓偈」の中に「滅此昏盲闇=仏は暗闇を滅する」という言葉があり、そこにも「盲」という字が使われ、
目の不自由なことを負のたとえに使った表現であると指摘された。
親鸞の和讃にもそれはある。「世の盲冥を照らすなり」と。「盲」という字が平然と使用され、障害者のことを
考えていない、その辛さ・苦悩を思いもしない表現となっている。親鸞にしてそうであるという限界を思わない
訳にはいかない。「めしいる」ということ、目の不自由な人、盲人は現実におられる。そのことを表わす言葉
として使用することには問題はないと思うが、「わからない」ということのたとえに「盲」という字を使うことは
明らかに誤りだと思う。
続いて、「悪しき業論」と呼ばれる内容について述べる。
〔一八〕で、釈尊が阿難に語りかける。「世の中の貧しい乞人を王のそばに並べるとしたら、
くらべものになるだろうか」。阿難は答えて次のように述べる。「いいえ、そのものを王のそばに並べた
ときには、その弱々しく醜いことはまったく話にならないほどで・・・そのわけは貧しい乞人は最低の暮らしをし
・・・ほとんど人間らしい生活をしていない。すべては、過去の世に功徳を積まなかったからです」と。
つまり、過去に悪いことをした罪で、死んだ後には地獄・餓鬼・畜生などの悪い世界に生まれて長い間
苦しみ、やっと人間世界に生まれても身分が低く最低の生活を営む・・・前世の業がもとで、現世の業と
なるというのである。この部分はインドの原本にはない。中国で加筆されたものと思われる。インドの原本
にないという点はよいと思うが、
いずれにせよ中国で挿入され日本に伝わって、これを読んだ封建時代の人々は、「被差別身分におかれた
人たちは自業自得である。あきらめよ」ととらえただろう。「そのために地獄へ落ち、やっと人間になっても
低い身分におかれるのだ」と断定しただろう。
このような内容のどこに仏教的なものがあるだろうか。人間として大切なものを目覚めさせる真実が
あるだろうか。「前世の因果が現世に報いとなってあらわれる」という「悪しき業論」を決定的に示していると
言わなければならない。
〔三一〕からの内容もインドの原本にはない部分である。同朋三者懇でともに研究している備後の学者が
調べた結果でも、原本にはないことを確認している。
特に問題なのは、〔三五〕から〔三九〕までにわたる、いわゆる「五悪段」と呼ばれる内容である。
それは次のような記述から始まっている。「第一の悪とは・・・五逆十悪の罪を犯して道にはずれている
ものは、後にその罰として自ずから悪い世界へ行かなければならない。・・・それでこの世には、
貧しいものや、身分の低いものや、心身の不自由なものや、才知の劣ったものなど様々な不幸な人がいる
のである。また、身分の高いものや、裕福なものや、才知のすぐれたものなどがいるのは、みな過去世で
人を慈しみ、親に孝行を尽すというような善い行いをして徳を積んだことによるのである」。
前世の業によって現世の幸不幸が決まるという論理である。それは明らかにおかしい。敢えていえば、
「今たとえこの世で身分が低くても善行に励み徳を積めば未来はよくなる、逆に今いくら王様だといばって
いても人を苦しめていれば今度は真反対にひどい目にあう」と解釈できなくもないが、この解釈にもかなり
無理がある。貧しく身分の低いものはダメ、身分高く裕福なものがよいと決めつけて価値を固定する見方に
もなるだろう。意味をくみ取るとすれば、「本能や欲望によって他者を蔑めば、未来に決していいことはない」
ということだろうか。それでもやはり「前世の個人の業が個人の現世を規定する」という教えであることには
違いなく、無量寿経の最大の問題だといえる。
このあたりで、次の「観無量寿経」の、いわゆる「旃陀羅問題」について述べたい。
釈迦が存命の頃の話である。「王舎城という城に阿闍世という王子がいて、父を恨み、牢に閉じ込め
飢え死にさせようとした。それを助けようとした母を怒って、阿闍世は母をも殺そうとした。そのとき、
聡明な大臣月光が同僚の耆婆とともに阿闍世王に申し上げた。『王位を望んで父を殺したものは
一万八千人もいるが、母を殺したものは一度も聞いたことがない。
王が母を殺すなら、王族の家柄を汚すもの。このようなことは旃陀羅のすることです』と」。
古代インドの四姓制度は、バラモン(司祭階級)、クシャトリア(戦士・王族階級)、ヴァイシャ(庶民階級)、
シュードラ(奴隷階級)で成り立っている。さらにそこに属さない「アウト・カースト」、または
「不可触賤民(アンタッチャブル)」ともいわれる、人間扱いされない身分の人々がいる。
歴史的にいえばアーリア人によって侵略されたトラヴィタ人などの原住民がその主なものである。
釈迦自身、アーリア人として侵略者の末裔といえる。釈迦は、四姓平等の教えは説いた。
しかしアウト・カーストであるチャンダーラ(旃陀羅)を含めた五姓平等を説いたかどうか。
チャンダーラにこそ、大きな悲しみをもち、解放の目を向けるべきではなかったのか。
釈迦が積極的にチャンダーラを導いたことが経典にあるかどうか、不明にして私はよく知らない。
後述するが、一部にそれに近いものがあるにはある。無視はしていない。しかし積極的とまでいえるかどうか。
話は戻って「母を殺すようなことは、旃陀羅のすること」と言われた阿闍世王。王は驚き、恐れ、
そしてついには剣を捨て、母を殺害することを思いとどまった。「母を殺す・・・そんな極悪非道な行いは
賤民身分のすることだ」という言語道断な決めつけ。それが阿闍世王に強烈なショックをあたえたのだ。
この観無量寿経を受けて、封建時代、学者が「旃陀羅は、日本でいえばエタ・非人のたぐい」と書き、
寺では説教でそのように語ってきた。これは大変な問題である。仏教が部落差別を残すことに
加担したといえる。水平社の井元麟之さんがそのことに対して何度も声を上げてきた。しかし今もなお
整理されていない。
同朋三者懇でも取り上げてきた。三者懇では「経典を絶対視してはならない」という見解に至っている。
親鸞は、この部分について歌にしている。「耆婆・月光ねんごろに 是旃陀羅とはぢしめて
不宜住此と奏してぞ 闍王の逆心いさめける」(浄土和讃・観経讃)。この中でも「旃陀羅は極悪非道なもの」
と決めつけられている。親鸞には、これは間違いだとはっきりと指摘してほしかった。それが見えていたなら、
「是旃陀羅」ではなく他の表現にしただろう。
先に述べた、釈迦は五姓平等を説いたかどうかという問題。釈迦は、旃陀羅に積極的伝道をあまりした
形跡がない。四姓平等は説いたが、五姓平等は説いていないと思う。ただ摩登伽経という経の中に、
次のような話がある。釈迦の弟子の阿難が、旃陀羅身分の女性と恋仲になり、様々ないきさつがある中で
阿難が身の危険を感じるようになり、それを釈迦が神通力で助け、旃陀羅身分の女性を尼僧にし、
仏弟子にしていく。旃陀羅であるということで無視するのではなく、仏弟子にするということで、
積極的ではないかもしれないが釈迦の平等観はうかがえるようだ。
月光も耆婆も、釈迦の教えを聞き、その信奉者であった。釈迦から平等観を学んでいるはずなのに、
「旃陀羅発言」をしている。釈迦の教えが浸透していないということだろう。釈迦が亡くなって500年以後、
観無量寿経は中国で作られたらしいと言われているが、涅槃経には阿闍世のことも出てくるので、
インドにあった話には違いない。「旃陀羅差別」が見えていたなら経典に残すことはあってはならず、
結局のところ経典作者の不明であり、差別・偏見を煽ることに加担した
内容となっていると言わなければならない。
|

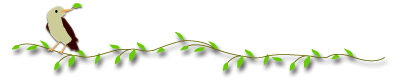
![]()
![]() ご意見・ご感想はこちら
ご意見・ご感想はこちら